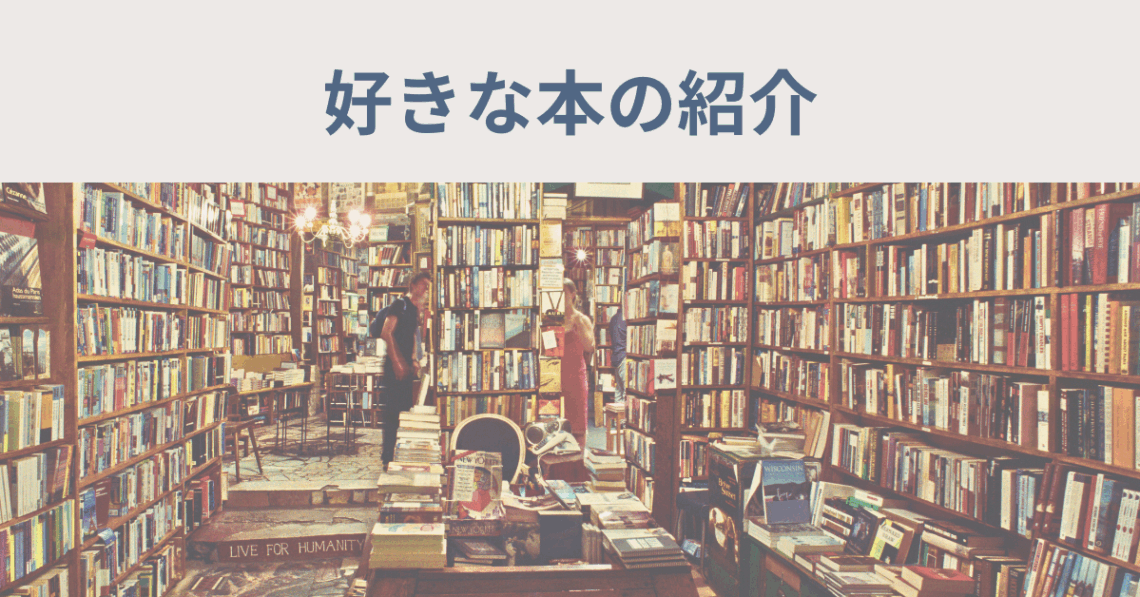
好きな本を紹介します – その1
こんにちは。「おしみな」小川です。
noteを始めて2回目。皆さんそれぞれに自分の個性を出して色々なテーマで投稿されてますね。自分はどんなふうに書いて行ったらいいかよく分からず、いくつかの切り口で下書きだけ5本くらい書いてみましたが、イマイチ公開する気になれずそのまま放置しています。
考えあぐねた末に、自分の読書経験でも書いてみるかと思い、家の本棚をじっと眺めてみました。といっても、多読家でもないし読んだ内容もほとんど忘れているので感想文にも紹介文にもなりませんが、私がどんな本が好きか(好きな著者、テーマなど)を書くことで、少し自分というものが伝わればと思います。
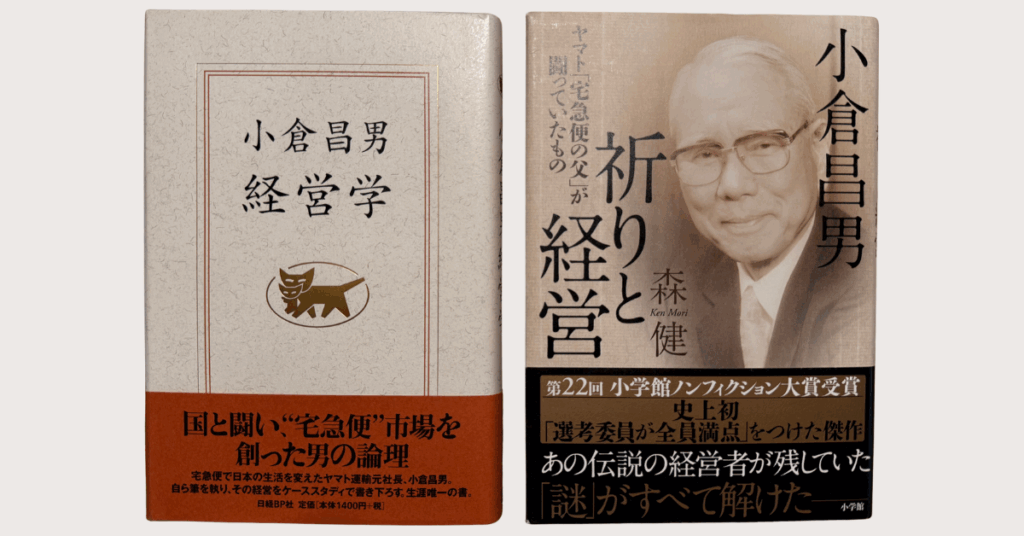
その第1回はこの2冊。左側のは宅急便を始めたヤマト運輸の小倉昌男さんの著書『経営学』(1999、日経BP社)。右側のはその小倉さんの晩年について緻密で真摯な取材に基づいて書かれたノンフィクション『小倉昌男 祈りと経営』(2016、小学館)。
『経営学』の方は、毎年の大学の授業の中で「必読書」として学生達に勧めているのだけど、実際に読んだ子がどれくらいいるかなあ笑?
『経営学』というタイトルがなんだか大げさに見えるけれど、中身は要するに、小倉さんがどういうきっかけで宅急便というサービスを考え、それを郵便局の小包というサービスしかなかった時代にどうやって日本全国に広め、生活に根付かせたかというストーリーが順番を追って書かれています。そのプロセスや苦難の道を書く中で、彼が大切にしていた考え方、経営哲学、矜持がはっきりと伝わってきます。
経営者としても、マーケターとしても
宅急便を始めた1976年のヤマト運輸もそれなりのサイズの会社でした(社員約5千人)が、あくまで関東地域を主なエリアとする運送会社でした。それが今では全国津々浦々まで誰もが知ってるあのトラックが走る、従業員17万人、売上2兆円近い、日本を代表する企業の一つになっています。最近では飛行機も飛ばしてる!
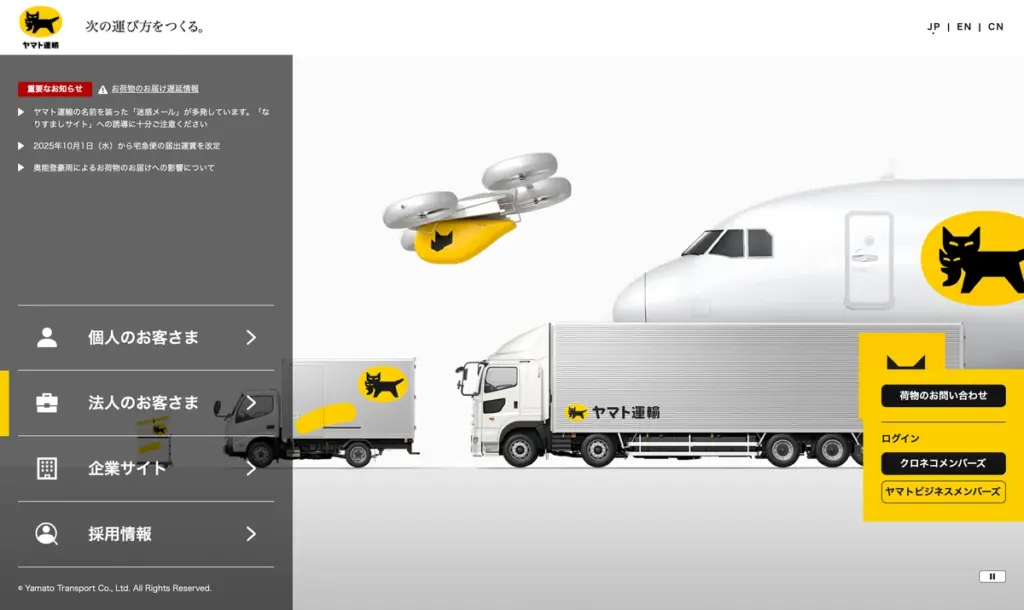
その第一歩を踏み出したのが小倉さんでした。
今だったら新しいサービスを始めようとしたら、まずはサイト作ろう、SNSで発信しよう、noteやろう(笑)(←あ、ヤマト運輸さんも公式noteされてるみたいですね、お見知りおき、よろしくお願いいたします)、ってなるんだろうけど、当時はそんな便利なツールはなく、超アナログな世界。今でも時々、街のお米屋さんやクリーニング店にクロネコヤマトの置き看板があって「宅急便受付ます」って書いてあったりして「何で???」て思う人もいるかも知れませんが、あれは理由があってそうなってるんですね。それは『経営学』読んでいただければ分かります。
ということで、経営学というより、第2創業者・社内起業家あるいはマーケターとしての小倉さんが成し遂げてきたことが事細かに分かります。
そして、それだけでなく、その過程で彼が大切にしてきたこと、特に経営トップとして、あるいはマーケターとして、あるいは一社員としても絶対に外してはならないことがはっきりと書かれています。今だったらオブラートにくるんだようなポリティカリー・コレクトな表現になるかもしれないような内容もものすごく率直に書かれています。
祈りと経営とは?
小倉さんがクリスチャンだったことは知っていたし、晩年には障害者の方たちの経済的自立と社会参加を助けるため、彼らが自分たちでパンを焼いて売る「スワンベーカリー」を立ち上げたことも知っていました。何年も前ですが、赤坂にあるスワンカフェ&ベーカリーに立ち寄ったこともあります(今ではあちこちに増えたみたいですね!)。
博愛精神の強いクリスチャンとはいえ、成功して大金持ちになった経営者が慈善事業として(節税のために?)始めたんでしょ?と最初は斜め目線で思っていましたが、『経営学』を読んで、単純に、やっぱり高い倫理観がある方だからだよなと思っていました。それで理解したつもりでした。めちゃくちゃ立派な、偉い方だよなー、と。
ところがしかし、そこに至るには、実はごく一部の人しか知らなかった、もっともっと深い理由があったのだということが『祈りと経営』を読んで分かりました。「謎が解けた」と帯に書いてあるとおりだと思います。どんな謎だったかは読んでください。あ、これ、アフィリエイトとかじゃないので、念の為笑。それにここまで取材した著者の方と、それを受け入れ出版することを認めたご家族や、恐らく会社の方々も立派だと思います。
『祈りと経営』の最後にも出てくるけれど、品川駅高輪口から坂を登っていった曲がり角のところに立派な教会があります。年に1回くらいだけど用があってその前を通ります。毎回「あーここが小倉さんの眠るところだ」と思い、心の中で手を合わせます。

